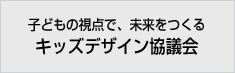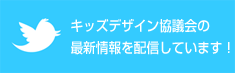審査を終えて
審査委員からのメッセージ
第19回キッズデザイン賞の審査を終えて、思いを寄せていただきました。
審査委員長

益田 文和
20年近く前、「子どもの安全」をデザインの条件に加えるために、キッズデザイン賞はスタートした。それは「子どもたちの幸せ」のための大前提であった。今日、「産み育てやすい社会」に向けて「安全に子どもを育てる手助けとなるデザイン」は多く見られる。その一方で、子ども自身に幸せをもたらすデザインがもっとあってもよいはずだ。子どもに希望をもたらすデザインが見てみたい。社会全体が「子どもが幸せな社会」を目指すのであれば、大人たちが楽になるだけでなく、子どもの心に直接働きかけるデザインがもっとあってもよい。客体から主体への視点の転換が必要だと強く感じている。
近代デザインは、経済活動の中で需要喚起の役割を果たしてきたが、デザインは本来それとは逆の力も持ちうるものである。今までのやり方ではなく、別の方法があるはずだと常に考え、提案していくのもデザインの役割だ。環境負荷の低減などは当然のこととして、「そんなにたくさんのものは必要ない」という価値観が共有できたとき、世の中に存在するものは大幅に減るかもしれないが、それでも残すべきは、経済的に豊かではない子どもたちに夢を与えたり、その子たちが育ったその次の世代の役に立ったりするものでなければならない。私たちは、「次へと続く世代のためにデザインをする」という覚悟を持つべきであり、キッズデザイン賞はそこに焦点を絞ることができるデザイン賞だと思っている。
副審査委員長

赤池 学
創設以来、20年目を迎えるキッズデザイン賞は、子供たちの安心、安全や、生み育てやすい社会づくりを実現する実践から、子供たち自身が主体的に社会人として多様な活動を行うインクルーシブな実践、祖父母世代、親世代と子供たち、そして近隣住民家族と積極的に交流、交歓するワーキング・トゥギャザーな実践へと進化してきた。主寝室と子供部屋、LDKからなる住宅を超えて、庭やウッドデッキ、大空間のなかで、親子3世代が調理、飲食、学習や余暇を楽しむ、新しい発想の企画住宅などが印象に残った。今後も、過去、子供が参画できなかった社会システムを子供たち自身が主人公として担う、チャーミングなデザイン実践を期待している。

持丸 正明
調査・研究分野の作品について言及したい。特定の障害などで特別な環境にある子ども、つまり市場経済の中では必ずしも対象数(N)が多くないものの、現実には非常に深刻な課題を抱えているケースに対して、しっかりと研究としてフォーカスを当てていた点が、まず評価できる。
次に良かった点として、今回の研究に限らず、そこで得られた知見を他の関係者が活用できる形にして普及を図っていることが挙げられる。学術論文として発表することも重要だが、それ以外の手段でも社会に成果を還元しようとしている点は、とても良かった。 後者の観点で言えば、単に「やって良かった」という感想で終わるのではなく、「何が良かったのか」「どういった知識が他の人にとって活用可能になったのか」といった点が、今後の研究においてより明確に示されると、さらに意義が深まるはずである。
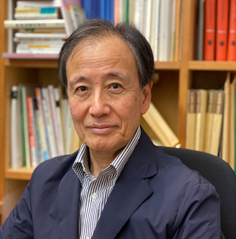
山中 龍宏
子どもの事故防止という点からコメントしたい。例えば、キッズデザイン協議会がこども家庭庁と連携して、乳幼児の死亡事故、とくに睡眠中の死亡事故などに対して新たな対策を講じるような取り組みも考えられるのではないだろうか。従来のセンサーとは異なる、新しい技術や仕組みに関する要望、あるいは課題の提起といった形でアピールしていくことも、一つの手段になるはずである。すぐに優れた解決策が得られるとは限らないが、「最低限、命を落とすような事故は防ごう」という強いメッセージは、もっと前面に出してもよいのではないかと思う。キッズデザイン賞は「デザインで社会課題を解決しよう」という目的を持つものであり、そうした思いを持つ事業者の方々にも共感してもらえるに違いない。
具体的な実行例として、たとえばベビーベッドからの転落事故の予防に関しては、現在のところ、見守り目的の機器以外に有効な器具がほとんど存在していない。「転落防止に特化した、子ども向けの専用製品を開発してほしい」といった要望を出すことも、十分に意義がある。こうしたテーマ特化型のデザイン賞であることも今後検討すべきと思う。
審査委員

赤松 幹之
調査・研究分野については、良い試みが見られた。現状をしっかり把握したうえで、それに対する解決策を示したパンフレットを配布する仕組みを整え、広めていくというアプローチは、調査・研究のあるべき姿のひとつである。
定量的な評価を行ったから調査・研究というわけではなく何が重要な課題であったのか、なぜそれが注目に値するのか、といった視点を示すことが大切だ。それが子どもを取り巻く環境の向上に寄与するための重要な視点であり、本分野の役割である。
一方で、多くの調査・研究で欠けていると感じるのは、「何がうまくいかなかったのか」という視点の提示であろう。失敗や課題が全くないという研究は現実的にはありえない。うまくいった点だけでなく、うまくいかなかった点をどう改善しようとしているかを記録に残していくことこそが次につながる重要なステップであり、うまくいかなかったであったことの表明がマイナスに働くことはない。そうした意識をもって、今後も調査・研究に臨んでいただきたい。

五十嵐 久枝
プロダクト分野の審査で感じたのは、全体的にデザイン性が落ち着き、無駄が減ってきているということ。ユーザビリティも非常に高まっており、素晴らしい傾向だと感じた。ベビーカーやマグ、保育園や外出先で使える小物など、産み育てやすい社会を意識したプロダクトが多く見られ、今後の希望を感じさせるものだった。欧米的なスタイルを取り入れつつ、日本独自の技術で軽量化するなど非常に優れた作品もあり、企業が子育てしやすい社会に対して、明確に意識を向けていることが伝わってきた。
また、文具に関しても興味深いものがいくつか見られた。なかでも鉛筆はこれからの進化に個人的に注目している。今回もアナログとデジタルの融合により、教育現場での活用が期待される作品があった。クレヨンも印象に残った。6色という限られた構成ながらも発色がとてもよく、太めの形状が色の魅力をしっかりと伝えてくれる点で、子どもにとってのインパクトが非常に大きいと感じた。
その一方で私は家具やインテリアを専門としているが、この分野では日本にある優れた技術が十分に活かされていないようにも感じている。日本に根付く家具づくりの素晴らしい技術がキッズデザインの文脈で活用され、世の中に広く注目されていくような動きがもっと必要だと思う。そのために応募される方々にもさらに積極的に投資をしていただき、良いプロダクトを社会へ広める姿勢が大切なのではないかと改めて感じた。

大月 ヒロ子
ワークショップや各種の活動プログラムを実践している立場から、今年の審査について感じたところを述べたいと思う。多くの作品を見ているなかで、子どもたちの発想をスタート地点にして、大人がそれにしっかり寄り添っていくサステナブルなプロジェクトが増えてきた点が今年の大きな特徴であり、収穫だと感じた。
こうした取り組みは子どもを中心として社会を組み立てていく、新しい価値観を育てていくことにつながるものであり、まさにキッズデザイン賞が目指しているところに適合している感がある。この流れが今後も続いていくことを期待したいと思う。
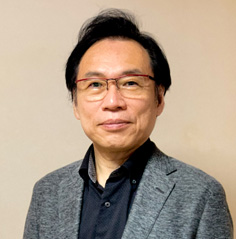
岡﨑 章
今回の審査を通して、特に印象的だった点が二つありました。 1つ目は、障碍のあるお子さんや小児がんの子どもなど、特別な支援を要する子どもたちに向けた取り組みが、これまで以上に多様化してきたことです。とりわけ注目したのは、健常児と障碍児の中間に位置する子どもたちへの提案です。彼らが社会との関わりや生きがいを感じられるように支援するツールや仕組みが増えてきたことは、非常に価値のある変化だと感じました。
2つ目のポイントは、評価における「思想」の扱い方です。審査の場では、ある作品をどのような視点や価値観で評価したかが表に出る場合もあれば、出ない場合もあります。社会的なテーマや課題に深く関わる作品では、「評価の文脈」が意図と異なって伝わってしまい、誤解や混乱を生むリスクもあります。応募作品には、社会課題に対する深い洞察と、多様な子どもたちに向けた真摯な取り組みが多く見られており、こうした優れた提案を正しく評価し、広く伝えるための評価基準や発信のあり方についても、より一層丁寧に検討していく必要があると感じました。

北野 幸子
子どもがただ守られ、支援される存在ではなく、自らの力で考え、行動し、学び、成長していく存在だという視点が大切であると考える。応募作品の中には、そうした子どもの当事者性や主体性を尊重し、子どもが何をしたいのか、自らどんな力を身につけていくのかに注目した提案が多く見られ、これはとても良い傾向だと思う。
同時に、その子どもの周りの大人たちもエージェントである、という視点も大切だ。子どもだけに焦点を当てるのではなく、子どもと大人の双方にとってやりがいがあり、嬉しく感じられるもの、互恵的な関係が成り立つような提案が望ましいと考える。誰かの自己犠牲に依拠する支援ではなく、大人の尊厳も守られる「子どもの権利の保障」を実現するようなデザインが増えていくことを望む。
そうした中で、科学的根拠や説得力ある知見に基づいた設計・運用が今後より強く求められていくと思う。審美的でかつ感性に訴える一方で、最新の知見や科学的根拠に裏打ちされたプロダクトや空間であるかを審査できちんと見極めていきたい。 もう一つ大切にしたいのが、地域格差や経済格差、情報格差といった社会課題への意識である。ある地域や環境における好事例が、他の環境や文脈においても展開可能かという普遍的要素を、評価にあたって意識していきたいと考えている。

定行 まり子
量産住宅を中心に審査を担当したが、全体的に作品の質は確実に向上してきている。重要なポイントは、集合住宅の提案であれば、建物が市街地とどう関係しているかということである。都市や地域でその住宅はどのように機能するのか、土地に適切な空間をどうつくるのかなど、周辺環境との調和や関係性が今後ますます重要になってくる。それを強く意識した空間提案に取り組んで欲しいと思う。
内部空間に関しては、共用スペースを含めた多様な工夫が見られ、非常に楽しく審査した。平屋建てで子どもたちの様子が見守れる空間設計や、空間の垂直方向を意識した動線や居場所の工夫など、子どもたちの行動や成長をしっかり考えた設計はとても面白く、評価できるポイントであった。
一方で、子どもの視点がやや抜け落ちていると感じる提案も一部に見られた。見た目やスペックだけではなく、「子どもがどのようにそこに関わるか」「どういう体験ができるか」という視点をさらに意識して設計に取り入れて、深みのある提案に進化させて欲しい。

竹内 昌義
キッズデザインを取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化してきている。子どもにとってのデザインとは何か、という根本的な問いについて、今一度立ち返って考える時期に来ているのではないだろうか。
いわゆる「子どもっぽい」デザイン、カラフルで派手な色使いだったり、幼さを強調するようなデザインではなく、子どもを一つの人格として尊重した上でのデザインのあり方を改めて考えていく必要がある。
今回の取り組みの中にも、そうした視点に踏み込んで丁寧に考えられているものがいくつも見受けられた。この流れを加速させるためにも、より多様な立場や背景を持った方々の参加があると良いと思う。
個人的には、教育のあり方が大きく変わる予感がしており、こうした流れとセットで考えるべき空間の在り方にもっと目が向けられるべきである。現状、教育の変化に比べて空間やデザインがまだ十分に追いついていない印象がある。そこに今後のキッズデザインの大きな可能性を感じている。

竹村 真一
『作品を通じて子どもをどこへ導いていきたいのか』を子どもに関わり、子どもを巻き込んだ活動をしている人は明確に持っていることが求められている。
子どもをどこへ導いていきたいのか、を考えることは、自分自身がどこへ行きたいのか、どんな人でありたいのか、どんな街に住みたいのか、を問い直す過程でもあるはずだ。DESIGNだけでなく、WHAT TO DESIGN、なぜこれをつくりたいのか、なぜこれをやりたいのかを今一度考えて欲しい。

中村 俊介
今年は障害やグレーゾーンにある子どもたちに向けたデザインが飛躍的に増えた。これは社会全体の流れともリンクしており、非常に歓迎すべきことである。一方で、頑張りを応援するだけに留まらず、本質的な課題を解決するデザインが求められるフェーズに来ていることも事実だ。当事者の尊厳を前提に、誰もが当たり前に使えるデザインへのシフトが必要だと感じた。
AIやテクノロジーが台頭し、それらは利便性を高めてくれる一方、副作用も伴うだろう。それをいかにバランスよくデザインに組み込むか、どうリスクを可視化するか、はキッズデザインの新しい課題になっている。大事なことは子どもにとって本当に良い未来をいかに描くか、であり、テクノロジーとデザインの両面からこの課題に真摯に向き合ったプロダクトやサービスが出てくることを期待している。最新テクノロジーが使える時代だからこそ、子どもにとってこんなに素晴らしい世界が開ける!というビジョンある作品をもっと見てみたい。

西田 佳史
現在、経済産業省では「消費生活用製品安全法」の運用が強化されており、乳幼児用の特定製品を対象とする新たなPSCマークが新設されるなど、わが国の子供の安全を守る仕組みが大きく変革されつつある。こうした背景を踏まえ、今後キッズデザイン賞に応募いただく際にも安全性に関する法的要件を満たすことを示すエビデンスを提示することがますます重要になってくると思う。キッズデザイン賞は創設以来、安全面にも力を入れてきたが、今後の審査においてもそこはしっかり堅持されるべきポイントである。 熱中症、やけど、交通事故、転倒、誤飲・誤嚥など、子どもが日常的に直面するリスクは多岐にわたり、製品の力で傷害予防を進める新たなイノベーションが期待されている。人工知能技術も大きく発展してきており、子どもの安全領域にも積極的にトライしていただきたい。
ここ数年の開催を見ると、意匠のデザインやユーザビリティは確実に向上している。一方、安全領域は、まだまだ発展の予知が大きく残されているように感じている。新たな安全分野を切り開くようなチャレンジを期待したい。

橋田 規子
プロダクトデザインにも関わっている立場から見て、今年は住宅設備に関する応募がやや少なかった印象を受けた。少し物足りなかったというのが正直な感想で、次年度以降は広がりを期待したい。
省エネルギーや空調関連の作品は一定数の応募があったが、「子どもを含めて使いやすいこと」や「表示が直感的でわかりやすいこと」といった視点は非常に重要だ。そうした配慮が感じられる応募があったことは良い兆しだと受け止めている。
子どもの危険防止を目的とした作品も一定数の応募があったが、プロダクトとしてのデザインのディテールをさらに詰めていって欲しいと感じるものも多かった。住宅の一部として使われる製品であれば、やはり外観的な調和や美しさも重要な要素であり、そうした観点からのステップアップも期待したい。
住宅関連では、例えば竣工後1年経っていれば、子どもがその空間でどのように動いたか、どのように使ったかといったエビデンスも残せるはずで、そうしたデータは審査を行ううえで重要な判断材料になる。住宅開発に伴い自然環境が失われていく現状についても、強く意識すべきである。その土地ならではの自然環境や地形の特性を活かした宅地設計や街づくりは、子どもたちの成長にとって有意義なものであり、将来的に大きな影響を及ぼすはずだ。30年後を見据えた視点で、「子どもの行動」や「自然との関わり」を踏まえた住宅設計が今後さらに増えていくことを期待している。

宮城 俊作
すでに「子どもだからこういうデザインでよい」といった時代ではない。現代の子どもたちは非常に多様な環境に触れて育っており、デザインやモノに対する"感度"や"基準"も、かなり高いと感じる。そうした変化を認識したうえで、子どもたちの視点や感性を尊重したデザインが求められているのではないだろうか。
現代の子どもたちは、小学校入学前であっても保護者の方針次第でさまざまな情報メディアに触れる機会が増えている。特にインターネットを通じて、単に情報を受け取るだけでなく、インタラクティブに関わる機会が増えている。私が懸念しているのは、こうしたデジタルメディアとのコミュニケーションが、実際には非常に限定的なプラットフォームへの依存にすぎないという点である。一見アクティブに見える関わりも、実は閉じた仕組みの中で与えられたものに従っているに過ぎず、それが本質的な主体性や多様な体験を阻害しているのではないかと感じる。結果、コミュニケーションの範囲が人間同士のやりとりだけに偏ってしまい、「人とモノ」や「人と自然」といった関係性が希薄になる。自然環境や実際の空間の中で、五感を通じて人やモノと関わる機会をもっと豊かに提供することが重要だ。キッズデザインでも、これからそうした視点を持った提案がもっと増えてくると良いのではないだろうか。
いずれにせよ、「子どもが参加しているから受賞できるかも」ではなく、「子どもを真ん中に据えて考えた結果、自然と価値あるものが生まれた」、そうした姿勢が評価されるべきである。

森本 千絵
個人的に特に印象に残ったのは「木製パレットを活用した循環する靴箱」の取り組みだった。子どもの発想から始まって、それに大人が自然に寄り添っていくようなアイデアであること、コミュニケーションのデザインとしての分かりやすさがあること、魅力的な形で継続して広がっていく力があること、がとても良い。
一方で、企業や行政と協働するチャンスがあってもデザインが残念な仕上がりになっているケースや、逆にデザインとしては面白くても一過性で終わってしまう取り組みも見受けられ、こうした点は今後進化して欲しいと感じた。
キッズデザイン賞という場を通じて、自分たちの取り組みだけでなく、他の企業や団体がどのような工夫をしているかを知り、それを自分たちの活動にどう活かしていけるかを考えることが大切。「学び合い」「共有し合える場」として、キッズデザイン賞の価値が広がっていくことを期待している。
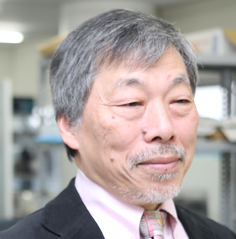
山中 敏正
審査の過程ではさまざまな議論があったが、そのなかで多様な視点が交わり、最終的にはとても意義深い議論ができた。その結果、子育てを支える側の人たち、つまり保護者や支援者たちが、もっと自然に無理なく子育てに力を注げる社会を目指すための取り組みにも一定の視点と期待を持って評価できた。厳しく見る部分はありつつも、良い芽を丁寧に育てていくという気持ちも忘れてはいけないと感じている。
改めて感じたのは、キッズデザイン賞の本質的な意義についてである。「子どものためのモノやサービスを評価する」だけではなく、「子どもをどう育てていくか」「どう未来の社会を担う人として力をつけていってもらうか」という視点こそが、この賞の本質なのではないかと強く感じた。
キッズデザイン賞は、子どもに何かを"与える"だけでなく、「子どもが力を発揮できるような環境や機会をいかにデザインするか」「未来を生きる主体としての子どもを、社会全体でどう支えていくか」を問う場であるべきだろう。その観点から見ると、企業や組織の活動そのものを評価するというよりも、活動を通じてどのような未来を描こうとしているのか、どのような社会の変化に寄与しようとしているのか、に注目したい。